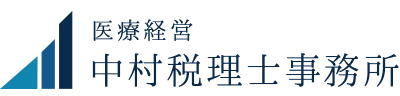認定医療法人の実務上の疑問点とはQ200
こんにちは。
「医療経営 中村税理士事務所」の中村祐介です。
今回も前回に続きまして、「認定医療法人」についてご相談を頂くことが多い点について、解説していきます。
「細かな要件があるのは知っているけど、実際はどう運用されているのかな。」
そうした先生も多いと思いますので、実務上の疑問点を中心に解説していきたいと思います。
※この記事は次の人におススメです
・認定医療法人に興味がある先生
認定医療法人の役員報酬はどう決まるのか
要件のひとつに「役員報酬が不当に高額でないこと」というものがあります。
支給基準が定まっていることを求められているわけですが、形式的なことのみならず、実際の金額はどうしたら良いでしょうか。
一般的に3,600万円とされていますが、厳密な上限が指定されているわけではありません。
とはいえ、実際には3,600万円のラインに収まることが多いと思いますので、それ以上の報酬が必要な先生は要注意です。
特別の利益を与えないこと
「法人関係者や株式会社等に特別の利益を与えないこと」という要件がありますが、ポイントは「特別な」ということです。
通常の利益であれば良いと解釈できますが、医療法人の運営上、役員社宅等に代表されるように、特別な場合が多いと思います。
取引の金額設定の根拠は問題ないでしょうか。
まずは認定医療法人の要件以上に、通常取引として成立しているか、ご注意ください。
MS法人との取引も同様です。
最近は「経営コンサルティング料300万円」のようなアバウトな取引は見受けられなくなりましたが、個々の取引について通常の利益であるか、事前に確認しておきましょう。
まとめ
申請期限に向けて間に合うように検討していくのではなく、申請する・しないに関わらず、検討だけでも早急にするべきです。
それは、事業承継全体に影響するからです。
どのような形で事業承継を行うか、大事な検討事項のひとつです。
株式会社には「事業承継税制」というものがありますが、医療法人にはありません。
事業承継税制は株式を代々渡していく制度ですが、当然、医療法人の出資持分はなくしていく方向(=持ち分なしへ移行させてたい)なので、この税制では持ち分なしへの移行が進まなくなります。
そのため、医療法人の場合、こちらの認定医療法人という制度を検討しなければなりません。
医療法人全体の約6割は、以前持ち分ありとなっています。
先生個人のためにも、後継者のためにも、そして地域医療のためにもしっかり検討していきたいですね!