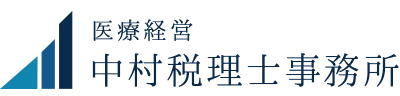10月からの消費税増税、医療機関への影響は?
最終更新日:2020年6月2日 全体像を把握しやすくするために、Q 34と統合して再編成しました。
こんにちは。
「医療経営 中村税理士事務所」の中村祐介です。
10月から消費税が10%に上がりました。
皆様の医療機関ではどのような影響が出ているでしょうか?
本格的な経営成績が出るのは11月上旬〜中旬になる病院が多いと思いますが、現場レベルではいかがでしょうか?
患者さんの財布の紐がきつくなり、受診抑制が起きたりしていないでしょうか?
「8%に上がった年は結構減収になったから、今回もしばらく減収になりそうだよ」
こうしたご意見の先生もいらっしゃいます。
そこで、今回は増税の影響と対応について、解説していきます。
ここは医療経営専門ブログではありますが、対比した方が分かりやすいですので、前半は社会全般の動きを中心に、後半は医療経営のみに絞って解説していきます。
※この記事は次の人にオススメです。
・消費税増税が医療機関に及ぼす影響をしっかり把握しておきたい人
・消費税増税にどう対応したらよいか、対策を考えたい人
静かな滑り出し
全体の印象として、静かな印象を持たれている方が多いと思います。
その要因は2つあります。
ひとつは増税が延期になったこともあり、大手企業を中心に準備の時間がきっちり取れたこと。
もうひとつは、政府の駆け込み緩和策によって、これまでの増税時にあったような「駆け込み需要」→「その反動で景気停滞」という流れが生まれにくかったこと。
それら以外にも、国民が消費税のアップに慣れてきた面もあるかもしれません。
初期対応では混乱も
とは言え、われわれ医療関係者よりも軽減税率対象品目を扱う小売業・卸業・飲食業は、対応に苦慮した面もあったようです。
例えば、よく言われる飲食店の「テイクアウトなら8%、店内飲食なら10%」という問題。
事前にかなりの時間を取って、社員やアルバイトの対応研修をしたようです。
レジでの対応のみならず、お客様から「あの人テイクアウト(8%)と言って購入した商品を店内で食べてますよ(10%)」と言った密告(!?)に対応するものまで、多岐に渡っていたようです。
「イートイン脱税」なる言葉や、そのイートイン脱税を指摘する「正義マン」なる言葉まで生まれたようでした。
対応面だけでなく、レジなどのシステム対応も必要になるため、見積もりを取って検討したり、補助金を申請したりと金銭面でも準備すべきことが多かったようです。
医療界では
その点、医療界では軽減税率の対象となる飲食料品を購入(交際費や福利厚生費、給食材料)することはあっても、消費税の課税売上とすることはほとんどないので、事前準備は比較的緩いものでした。
それは、医薬品が軽減税率の対象にならなかったという点が大きいと思います。
例えば、医薬品に該当しない健康食品や栄養ドリンクは「食品」に該当し、軽減税率ですが、病院で扱うことはほとんどないでしょう。
類似として、特定保健用食品や栄養機能食品、機能性表示食品はあくまでも医薬品ではなく、「食品」に該当しますが、やはり、病院がメインに扱うものではありません。
とは言え、何もしなくていいわけではありません。
区分記載請求書等の確認・保存は必要
たとえ軽減税率対象品目を全く扱わない業種であっても、購入することはあると思います。
そのため、区分記載請求書等(Q24「区分記載請求書等保存方式は病院・クリニックでも必要か?」をご覧ください)の確認や保存は必要になりますので、ご注意ください。
①軽減税率対象品目である旨の記載はあるか
②税率ごとの合計した税込金額の記載はあるか
③請求書等に基づいて、会計ソフトへ税率区分ごとに入力できているか、帳簿へ記載できているか
特に、①と②の記載のない請求書をもらってしまった場合、購入側で追記した方が良いと思われます。
社会編のまとめ
医療機関の経営に及ぼす影響については次回見ていきますが、前半は対比の意味で、医療界以外を中心に見ていきました。
軽減税率をメインに扱うことのない医療界においても、上記の区分記載請求書等の確認や保存は必要です。
仮に区分記載請求書等を発行する場合には、記載の不備がありますと、相手の事業者に追記させなければいけないことになります。
これは、追記が「追記することができる」とありながら、実質的には義務規定となるためです。
相手先に事務負担を強いることになり、迷惑をかけてしまいますので、気をつけたいですね。
3つの影響
後半は医療界について、解説していこうと思います。
病院やクリニックに及ぼす影響は下記の3つではないでしょうか。
(1)受診抑制
(2)支出の増加(8%→10%)
(3)収入の増加(初診料や再診料等の点数アップによる補填)
まず、「受診抑制」ですが、皆様の医療機関では受診抑制の傾向が出ていますでしょうか?
「まだ10月だし、増税の影響か分からない」とお考えかもしれませんが、9月に駆け込み受診が起きたのであれば、受診抑制が起きている可能性がありますが、駆け込みがなかったのであれば、受診抑制とは考えづらいでしょう。
実際、私の周囲では受診抑制の声はほとんど聞こえてきません。
支出の増加を計算してみる
次のふたつめの「支出の増加」です。
これは確実に影響が出ていると思います。病院の支出の大部分は給与関係であり、そこには消費税はかかりませんが、それでも3割くらいは消費税のかかる取引になりますので、支出は増えてきます。
これは簡単に計算できます。
①病院の支出の中から、消費税のかかる取引をピックアップ(月次決算書の勘定科目単位でOK)
②その税込金額を「×100/110」をして、税抜金額にする(税抜経理の場合はそのままでOK)
③税抜金額×2%をする
この金額が増税によって増えた支出です。
これを次で解説する収入の補填額と比較することで、経営上の影響を試算することができます。
収入金額の補填額を計算する
消費税の増税に伴って、診療報酬も改訂されています。
これも計算することができます。
「初診料や再診料などの改訂によって増えた単価の差額×算定件数」です。
この金額が増税に伴う補填による「収入の増加額」です。
影響の大きかった病院・クリニックとは
上記の「増加した支出」と「増加した収入」を比較してみてください。
多くの病院ではそれほど、大きな差額は出ていないと思います。
ただし、それなりの影響が出た病院やクリニックもありました。
(1)初診料や再診料の算定が少なかった
そもそもの病院の機能などにもよりますので、致し方ない部分もありますが、来月以降も引き続き影響が出てしまうと見込まれます。
引き続き、連携の推進・紹介の強化、もしくは、病院の経営体質の改善に努めたいですね。
(2)大きな支出があった
多くの医療機関では、大きなものは9月中に購入・支出を済ませていました。
ただ、機械の修理等予測できないものもあり、大きな支出が出た医療機関では支出の増加が大きくなり、診療報酬の補填ではまかないきれない状況となりました。
この部分については、税制でフォローすることになっています。
昨年度の税制改正でできた下記の3つと設備投資の3本柱とも言える3つを合計した6つの税制の適用を検討することが大切です。
(1)昨年度改正
①高度医療機器の取得(MRI・CTの適正配置と有効利用の要件追加)
②働き方改革推進の観点から勤務時間短縮につながるもの
③地域医療構想実現のための病床再編
(2)設備投資3本柱
①中小企業投資促進税制
②商業・サービス業・農林水産業活性化税制(介護事業を前提)
③中小企業経営強化税制
医療編のまとめ
消費税の増税は診療報酬で補填することが基本線となっていますが、大きな支出が出る時はそうはいきません。
その場合のために、上記の設備投資に関する税制が出来ています。
診療報酬の補填と設備投資税制の両輪で対応しようという方針です。
必ず、使い忘れることがないように、そして、上手に適用を受けることで設備投資の効果は最大化されます。
大きな経営判断をする際には、必ず信頼できる専門家に相談するようにしましょう。