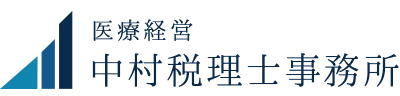医療法人及び個人開業医の社会保険とはQ210
こんにちは。
「医療経営 中村税理士事務所」の中村祐介です。
医療法人や個人開業医などの医療機関において、社会保険料の負担が少しずつ増してきていると思います。
雇用している職員様側においても、税金の非課税ラインが上がったことによって、社会保険の扶養のラインも気になっているところかと思います。
そこで今回は税務や医療経営から少しだけ離れ、社会保険についての基礎知識をまとめていきたいと思います。
※この記事は次の人にオススメです
・医療法人の理事長先生及び個人開業医の先生
健康保険は
まずは健康保険です。
国民健康保険は基本として、「医師国保」、「協会けんぽ」または「健康保険組合(例:東京都医業健康保険組合)」のいずれかかと思います。
「医師国保」は個人開業医が前提となりますが、一定条件のもと、医療法人になっても適用除外申請によって「医師国保」のままでいることが可能です。※年金は厚生年金へ
常時5人以上の個人開業医も同様です。
医師国保のメリットは保険料が安いことと家族を扶養にしやすい(所得判定なし)こと。
デメリットは自家診療ができないことと給付の手当金が薄いことが挙げられると思います。
所得の多い先生にとっては、所得に関係なく、保険料が一定である点が魅力かと思います。
反対に職員様にとっては固定の医師国保の方が高いケースもありますので、注意が必要です。
また、「協会けんぽ」は多くの先生が加入しています。
「健康保険組合」はそれより保険料が安いことが多いですが、扶養の判定が厳しい傾向もあるようです。
年金は
次に年金です。
医療法人として厚生年金、個人開業医として国民年金となります。
結果的に、厚生年金の医療法人の健康保険は「協会けんぽ」または「健康保険組合」もしくは「適用除外と受けて医師国保」というセットになります。
また、国民年金の個人開業医は「国民健康保険」または「医師国保」というセットになります。
最後に
医療機関の人件費はどんどん増えてきています。
それに伴い、社会保険料も比例して増えています。
社会保険に関する相談は顧問の社労士さんにするとしても、基礎知識は持っておきたいですね!