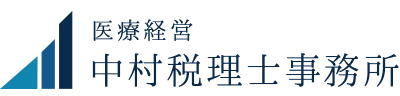医療法人の持分が事業承継の第一歩?
※最終更新日:2025年9月4日
医療法人の事業承継の問題は何でしょうか?
それは、二つの問題からなります。
ひとつめは、後継者不足です。医療法人の理事長は必ずしも、医師である必要はありませんが、事業を承継するという観点から考えると、医師であることが望ましく、また、現場の統率などを考えても医師である方がうまくいくケースが多いのが実情です。
そして、もう一つの問題がこれから解説する出資持分の取り扱いです。
出資持分の評価が大きくなり過ぎていて、払い戻しの金額や相続税の負担が過大になっているケースをよく見かけます。
そこで今回は、出資持分対策を中心に、医療法人の事業承継について解説していきます。
※この記事は次の方にオススメです
・医療法人の事業承継を考え始めた人
・医療法人の事業承継について、基本となる持分や社員について学びたい人
問題となるケースはひとつ
医療法人の出資持分の評価で問題となるのは、当たり前ですが、持分がある医療法人です。
平成19年4月以降、設立される医療法人はすべて持分のない医療法人ですので、この問題は生じません。
ただし、現存する医療法人のほとんどが、旧制度の持分のない医療法人ですので、この問題への対策が必要になってきます。
(1)対策が必要な医療法人
平成19年3月31日以前に設立された持分ありの医療法人
(2)対策の必要ない医療法人
上記(1)以外の医療法人
例:平成19年4月1日以降に設立された医療法人、基金拠出型医療法人、特定医療法人、社会医療法人、財団医療法人
持分が問題となるケース
この持分が問題となるケースは大きく分けて、2パターンが想定されます。
(1)持分を払い戻すとき
医療法人の持分を払い戻すのは、自由にできるわけではなく、
①持分を持つ社員が退職したとき(払戻請求権)
②医療法人が解散したとき(残余財産分配権)
このケースに限定されます。特に怖いのが、①の社員が退職した際に、払い戻しを請求され、その金額が膨大になるケースです。
以前の訴訟では、普通のクリニックで3億円を超える金額を請求されたというケースがありました。
3億円用意できるでしょうか。
仮に用意できたとしても、その後経営に影響はないでしょうか。
こうした理由から、出資持分の評価が上がり過ぎないように、対策が必要となります。
その具体的な解説は、次回以降をご覧ください。
払戻請求権は「できる」規定であるため、行使するかどうかは社員の意思次第です。
反対に、「残余財産分配権」は「できる」規定ではないため、解散時には必ず分配することになります。
(2)相続財産となったとき
もうひとつ問題となるケースは、出資持分を持った社員が相続を迎えたケースです。
その出資持分は相続財産となります。当然、高額な出資持分には、高額な相続税が課税されます。
この点からもやはり、出資持分が上がり過ぎないような対策が必要となります。
具体的な対策の解説は上記(1)と同じになりますので、次回以降をご覧ください。
社員とは
補足ですが、社員とはどういうものでしょうか。
それは、株式会社で言う株主のようなもので、いわゆる職員ではありません。
ただし、医療法人に出資する義務はないため、社員であっても持分を持たない方もいらっしゃいます。
反対に、持分を持っていても、社員でない人もいます。
そこで、「株式会社で社員になって、医療法人に出資しても良いか」というご相談をよくお受けします。
ご回答ですが、「出資自体は可能ですが、社員になることはできず、社員総会で決議に参加したり、経営に参画することはできない」ということになります。
つまり、払い戻しを受けることはできません。
社員でないため「払戻請求権」はありません。あるのは「残余財産分配権」のみです。
社員は払戻請求権を持つだけではなく、議決権も持つことになります。
そのため、医療法人の経営者以外の人が持つことは将来のリスクにつながります。
社員になるには、医療法人の社員総会の承認が必要です。
医療法人の種類によっては同族経営ができないものもありますが、そうした規制がない医療法人であれば、経営者や後継者を中心とした社員構成になるように、気をつけて運営しましょう。
まとめ
今回は医療法人の事業承継について、その前提となる考え方について解説していきました。
「持分があるから問題なんだ」として、持分のない医療法人へ移行する方も増えていますし、それを国も推奨していて、「認定医療法人」として期間を限定して制度化しています。
ただし、持分は財産権でもあります。これまでの努力の蓄積である財産権を放棄する必要が本当にあるのでしょうか?
実務上は、移行しなくていいケースも多くあります。
ただし、出資持分の評価が上がりすぎないように対策をした上で、という条件は必ず付きます。
その対策をした上で、移行するのであればいくつかある移行方法のうち、最も適したものを選ぶようにしましょう。
このブログでは、「事業承継」のカテゴリーで、順次解説していきますので、引き続き、ご確認ください。